キンメダイとはどんな魚

| |
| キンメダイはスズキ目に近いが、キンメダイ目として独立していて、キンメダイ目キンメダイ科に属する。鮮やかな朱色で、目が大きいのが特徴の深海魚である。また名前の由来は新鮮なときの、目が金色をしているので「キンメダイ」と言われている。 |
起源は古く、中生代・白亜紀から化石が知られている。つまり、イワシと同時代から存在する魚である。
生息領域は太平洋・インド洋・大西洋など温帯域から熱帯域に分布し、世界の大洋に広く分布するが、わが国周辺で は北海道釧路以南の太平洋岸や東シナ海、遠くは台湾、フィリピン沖、さらにはメキシコ湾にも分布していて、日本海 側では富山湾や新潟沖で漁獲された記録がある。おもな漁場は銚子沖・房総半島 沿岸・相模灘・伊豆半島東岸・ 伊豆小笠原海嶺・室戸沖・紀南礁・南西諸島などで大陸棚や海山周辺の水深 200~600mに生息している。1年中殆んど切れ目なく築地の市場に入荷している。
|
| キンメダイは生後4年で体長(尾叉長)約34㎝になり成熟する。関東近海では勝浦沖や相模灘でも産卵するが主な産卵場は高齢魚が多く分布する伊豆小笠原海嶺であろう。産卵期は7~10月(盛期は8月)と推定されている。多回産卵で、熟卵数は体長40㎝で280万粒とされている。生まれて間もない前期仔魚は50m以浅の表層に分布するが、その後の採集例は少なく、生態は良く解っていない。 |
12月から2月に捕れるものが身も締まり、脂が乗って美味で、あっさりとした風味で、姿形と色の美しさもあり、地方によっては縁起物扱いされている。
新鮮なものは刺身に、その他煮付け・塩焼き・ちり鍋・粗煮など、どのように調理しても美味しい人気のお魚です。
|
| 庶民が口にするのようになったのは戦後のことだろうか。とくに西日本では、赤い肌色が金魚に似ていることから、ごく最近まで、キンメダイを食べる食習慣がなかったらしい。 |
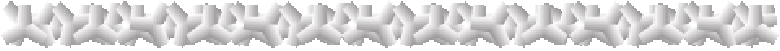
| |
| キンメダイも最近は目に見えて少なくなってきているようで、ある漁業者は、「漁が少なくなり、魚も小さくなってきた。」 ある人は、「三宅島の噴火の影響ではないか。」とも言っています。また、ある学者は、「伊豆諸島近海で釣られるキンメダイは、この海域で産卵されたものばかりでなく、鹿児島や沖縄など黒潮の上流域から流れて来た物もあるのではなか。」とも言っています。 |
| キンメダイが捕れなくなると、漁業者や釣り人ばかりでなく、長年、キンメダイを楽しく賞味してきた人々や、キンメダイのブランドを守ってきた多くのお店の人達に大変な影響を及ぼすことになります。 |
| 皆さんと共にこれからもキンメダイを乱獲することなく末永く資源保 護をしていきましょう。 |

| |

| |
| |
1)産卵
|
キンメダイの産卵期は夏期で、40cmの雌で約280万粒の卵を産むとされています。
|
| 2)成長 |
キンメダイの卵は大きさが1.1mmほどで、油球の色がピンク色~オレンジ色をしているのが特徴で、深海で産み出された卵は、海面まで浮上し、22~3日でふ化します。
ふ化したキンメダイは約2,3mmほどで、まだ目も見えず、口もないので卵黄の栄養で成長します。
|
| ①前期仔魚(全長2.5mm) |
| 数日後、目が見えるようになり、口も開き、餌をとるようになり、この頃腹ビレの伸びるのがキンメダイの特徴です。 |
| ②後期仔魚(全長3.7mm) |
| ③稚魚(全長11mm) |
| 1,2歳の若いキンメダイは背ビレが長く伸び、糸ヒキキンメと呼ばれ、成魚に比べて少し浅いところに暮らしています。 |
| ④若魚(尾叉長約18cm) |
| 4歳頃になると、成熟して産卵に参加します。 |
| ⑤キンメダイ成魚(尾叉長40cm) |
|